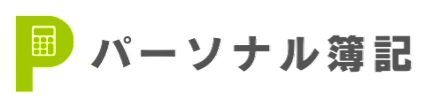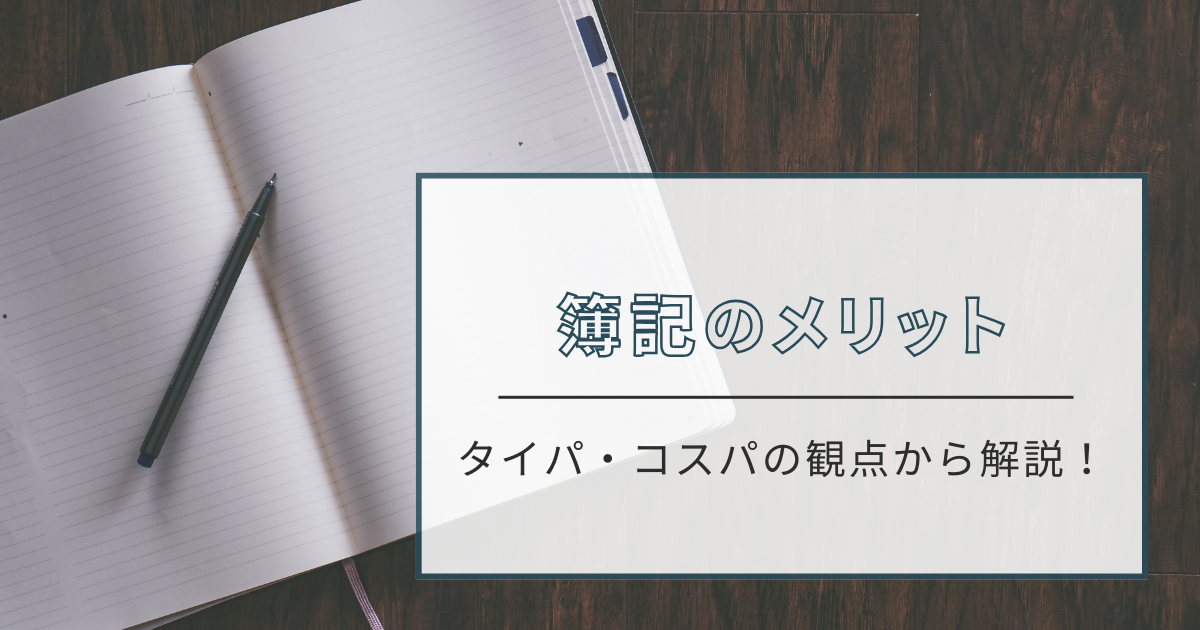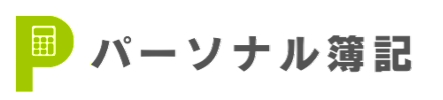簿記は年間約50万人が受験している、超人気資格です。
何か資格を取りたい!と考えたとき、TOEIC・英検・宅建などと比べて、検討したことのある人も多いのではないかと思います。
「勉強して損はないよ!」と簡単に言うこともできますが、
・簿記以外にも複数の選択肢があること
・時間や労力、費用がかかること
を考え、簿記を取ることで得られるメリットがコストを上回るか?検討する必要があります。
納得して自分の意志で始めないと途中で挫折してしまいます。
本記事を読んで、納得した上で勉強を始めてもらえたら嬉しいです。
同時に「自分には、メリットよりコストの方が大きいな…」と感じたら、別の道へ進むこともアリだと思います。
人生は有限です。
-
簿記を取るメリットは?
-
3種類のメリットがあります。
- ビジネス(会社員、経営者)に役立つ
- 会計的思考が身につく
- 人生の成功体験になる
-
コスト・パフォーマンス、タイム・パフォーマンスは良いの?
-
簿記3級はほとんどの人にとってコスパ・タイパが良く、2級は人によって異なります。
-
デメリットはある?
-
1級の場合、コスパ・タイパともに高い人の方が少ないので、注意が必要です。
また、中途半端に勉強すると、時間もお金も浪費します。
目次
ビジネス上のメリット
何よりも分かりやすいメリットです。
まずは会社員の方を前提に話を進めますので、経営者の方・将来独立したいと考えている方は、こちらからご覧ください。
就職・転職で有利
目に見えて分かりやすいメリットですね。
就職・転職へ備えて、簿記の勉強を始めようと考えている人も多いのではないでしょうか。
一口に「有利になる」と言っても、実際には3段階のレベルがあり、会社や職種によって異なります。
- 必須(★★★)…簿記を持っていないと応募できない
- ないと不利(★★)…必須ではないが持っていることが普通なので、持っていないと不利になる
- あると有利(★)…持っている人が少ないので、持っていると有利になる
| 簿記が必須(★★★) | 簿記がないと不利(★) | 簿記があると有利(★) |
| 経理部 会計事務所 会計コンサル ※派遣社員を除く | 金融業界 会計商品を取り扱う会社 (会計ソフトなど) 会計以外のコンサル | 経営企画部 商社 など |
どの会社でも必ず存在する経理部、会計を生業としている会計事務所、会計コンサルなどは、簿記が分からないと仕事になりませんから、有利になるというよりは、必須になります。
銀行・証券会社・保険会社といった金融業界、会計商品を取り扱う会社、コンサルなどは、持っていることが比較的普通なので、持っていない人は逆に不利になります。
簿記を取らないと出世できない会社もあります。
※他の要素(学歴や実務経験)でカバーして入社後に簿記を取る人もいます。
それ以外の会社は、持っている人が少ないので、簿記の知識があると有利になります。
有利になる度合いは、業種・会社・職種によって異なりますが、例えば経営企画部などは評価されやすく、全く関係のない理系の研究職などは、ほぼ評価に影響しないと思われます。
年収が高い
うっすら気づいた方もいるかもしれませんが、簿記を使う職業は平均年収の高いものが多いです。
✔ 職種別平均年収ランキング
| ランキング | 職種 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 専門職 (コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 598万円 |
| 2 | 企画/管理系 | 543万円 |
| 3 | 営業系 | 456万円 |
| 4 | 技術系(電気/電子/機械) | 455万円 |
| 5 | 技術系(IT/通信) | 452万円 |
| 6 | 金融系専門職 | 452万円 |
| 7 | 技術系(建築/土木) | 432万円 |
| 8 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 395万円 |
| 9 | クリエイティブ系 | 383万円 |
| 10 | 事務/アシスタント系 | 343万円 |
| 11 | 販売/サービス系 | 334万円 |
職業選択において年収に重きを置く人は、簿記を勉強し平均年収の高い職種を目指すのもアリです。
数字の分かる経営者になれる

実は決算書(*)の読めない経営者は、ざらにいます。
*会社の状況を定量的に表す報告書
数字のことは税理士・CFOに一任していて、自分は最低限の数字だけ把握している、という方です。
結果的にそれで回っている会社も多いですが、決算書を読めた方が良いのは言わずもがなですよね。
決算書というのは、投資家や債権者などの利害関係者へ報告することが主目的ですが、経営者が経営判断へ役立てることも目的の一つです。
税金の調整など細かいことまで知らなくとも良いですが、せめて決算書を見て会社の状況が定量的に理解でき、経営判断ができるようになるとより良いですね。
たまに自社の原価率も分かっていない経営者の方もいらっしゃいますが、これでは経営の改善ができません。
ちなみに経営者に役立つ資格として、簿記検定以外にビジネス会計検定というものがあります。
簿記検定は決算書の作成方法を学ぶのに対して、ビジネス会計検定では決算書の分析方法を学びます。
ビジネス会計検定は経営者向きの試験ではありますが、会計の考え方を習得する、という意味では物足りず、表面的な理解(暗記)に止まってしまう可能性がありますので、まずは簿記で基礎知識を学ぶことをお勧めします。
急がば回れ、です。
会計的思考が身につく
ここからは一見分かりづらいメリットになります。
簿記には、単式簿記と複式簿記の2種類があります。
例)銀行から借り入れをして現金1,000,000円を手に入れた場合
違いが分かりますか?
単式簿記の方は、現金収支にだけ注目しているので、本業で儲かったお金であろうと、借りてきたお金であろうと、同じように考えます。
複式簿記の方は、手許の資産が増えたものの(+)、同時に将来の返済義務を負う(-)、と二面的に捉えています。
簿記検定では、複式簿記の方を習いますので、これらの考え方が染みつきます。
少し飛躍した論理になりますが、複式簿記を習うと数字周りで騙されにくくなると思っています。
怪しい投資話を持ちかけられた時に、一面的な話を鵜呑みにせず別の観点から考えてみたり、自分でも調べなら計算してみたりできるのではないかと個人的には思います。
人生の成功体験になる

人生経験になるからと言って簿記を勉強する人は少ないと思いますが、副次的な効果として考えていただければと思います。
あなたはこれまでの人生の中で、成功体験はありますか?
部活で優勝した、大学受験に合格した、仕事で成功した、など
子供の頃は、新しいことばかりで、小さな成功も嬉しく感じていたと思います。
しかし、大人になってからどうでしょうか?
新しいチャレンジ自体も少なくなり、チャレンジするにしても家庭や仕事など制約があります。
そんな中で苦労して簿記検定に合格すると成功体験として嬉しいですし、自信にもなります。
「簿記は簡単」という人を時々SNSで見かけますが、実際に勉強し始めたら「普通に難しいじゃないか!」と感じる人が大半です。
最初は「本当に合格できるのだろうか…」と不安になると思います。
勉強をしている時も挫折しそうになる場面が何度かあるはずです。
そこを乗り越え合格した時は本当に嬉しいものです。
自分を褒めたくなります。
大人になってから減った成功体験を経験することができます。
タイパ・コスパの観点から簿記のメリットを検証!
ここまで簿記を学ぶことのメリットをお話してきました。
とは言っても、明日さくっと取れる試験でもないですし、ある程度の費用・時間・労力がかかります。
これらを上回るメリットであるかは別の話です。
ここからは、コスト・パフォーマンス、タイム・パフォーマンスの観点から、簿記を取る意味があるのか検証していきます。
| 受験級 | 学習時間 | 労力 | お金 |
|---|---|---|---|
| 簿記3級 | 約100~150時間 ※パーソナル簿記では50時間 | 学生or社会人で異なる | 独学:教材費 数千円 スクール:約2万円~ |
| 簿記2級 | 約300~500時間 ※パーソナル簿記では150時間 | 学生or社会人で異なる | 独学:教材費 数千円 スクール:約6万円~ |
毎日1時間勉強するとしたら、簿記3級は約4か月、簿記2級は約1年かかります。
「イメージよりも大変そう!」と感じた人が多いと思います。
労力は人によって違いますが、例えば若い学生が1時間勉強するのと、社会人が仕事や家庭と両立しながら1時間勉強するのとでは、労力(体力)に差が出ると思います。
費用については勉強方法によって異なりますが、費用と時間は一般的にトレードオフの関係にあります。
スクールを使えば費用はかかりますが時間は短縮でき、逆に独学にすると費用は抑えられますが時間がかかります。
例えば、弊社パーソナル簿記では、37,400円~74,800円/月で管理型の個別指導を行っています。
独学よりも費用はかかりますが、簿記3級は約50時間、簿記2級は約150時間で、皆さん合格しています。
これらトータルのコスト(時間・労力・お金)に対して、得られるメリットは大きいでしょうか?小さいでしょうか?
人によって結論は変わると思いますが、合格した人の中で「そこまでして取らなくても良かったな…」と後悔している人は少ないです。
タイパ・コスパが悪くなる場合
逆にタイパ・コスパの悪いケースがありますので、お話します。
簿記1級は相当な覚悟が必要
簿記1級は本当に難しいです。
合格率は約10%で、1,000~2,000時間の学習時間が必要だと言われています。
目指すのであれば私生活を犠牲にする覚悟が必要です。
一方で合格した場合のメリットですが、職種によって大きく評価されたり、相当な会計知識が身につくことは間違いありませんが、どこまでいっても公認会計士や税理士のように独占業務ができるわけではありません。*
*決算書の監査は公認会計士の独占業務、税務書類の作成等は税理士の独占業務
「簿記1級がないとできない仕事」は法律上ありません。
相当なコストの割に、合格可能性が低く、得られるメリットが不確実であることから、簿記1級はタイパ・コスパは良くありません。
一般的には、税理士や公認会計士が途中経過として取るケースが多く、士業を目指さず簿記1級を最終ゴールとするのであれば、相当な覚悟が必要です。
※時間とお金に余裕がある人、純粋に簿記を勉強したい人は、簿記1級の勉強も素晴らしいと思います!
中途半端に勉強しないで
これまで合格することを前提と話してきましたが、結果不合格に終わったり途中で辞めてしまっては元も子もありません。
簿記3級の合格率は約40%、2級は約35%です。
決して高くはありませんが、正しい勉強法で十分な勉強時間を取れば合格できるレベルです。
しかし、途中で勉強するのをやめてしまったり、誤った勉強法で不合格になり諦めてしまったら、努力が無駄になるとまでは言いませんが、コスパ・タイパは大幅に下がってしまいます。
勉強すると決めたのなら最後までやり切りましょう!
まとめ:簿記3級の早期合格がコスパ・タイパ◎
人によって簿記取得のメリットやその度合いは異なりますが、簿記3級を短期間で合格する分には、ほとんどの人にとってコスパ・タイパが高いと思います。
簿記とは、会社がどんな活動を行っていて、どのように記録していくのか?を学んでいきますので、
会社で勤めていたり経営している限り、ほとんどの人にとって大なり小なりメリットがあります。
なおかつ、短期間の勉強で済ませてしまえば、コストも抑えられます。
一方で、簿記2級は人によって大きく異なりますので、よく考えて納得した上で始めましょう!
弊社(パーソナル簿記)では、社会人の短期合格を目指し、管理・個別指導を行っています。
無料の学習相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。